「着心地はどうかしら?」
「すごく素敵です、さすが先輩。」
「・・・気に入ってもらえた?」
「もちろん!」
「よかった〜!」
「ありがとうございます。これで冬まで楽しめます。」
外苑の少し外れの、一見古い洋館かと思うような煉瓦づくりの建物。
大きな鏡の中で、涼子は先輩である間中朋子に向かって笑いかけた。
「涼子ちゃんは年々きれいになるから、着いていくのが大変だわ。勉強させてもらっているの。」
「先輩こそ、すっかりお店を切り盛りされて、すごいです。
ここで作ったお洋服だと言えば、もう海外でだって通用しますよ。」
涼子と間中朋子とは、高校の先輩後輩だ。
朋子は高校の時から、何かといえば少し浮き気味だった涼子にも分け隔てなく気を使ってくれ、
周囲からの人望も厚かった。
だからこそ、彼女が本格的にデザイナーとして、
父親の会社に新しいオーダーメイドのブランドを立ち上げた時、
母校の卒業生たちはこぞって彼女のところに服を仕立てに向かった。
その中でも、彼女の名声を一気に不動のものにしたのは、
宝石商の娘であり、TVアナウンサーから一躍海外富豪の婦人となった、
橘栞のウェディングドレスだった。
そのドレスは世界に報道され、店にはまさに人が押し寄せたのだった。
「忙しいんでしょう?」
「少し落ち着いたのよ。大丈夫。仕上がりが遅くなってごめんなさいね。」
「いいえ、ちっとも遅くなんてないわ。」
それだけ店が混んでも朋子は、「涼子ちゃんは忙しいから」と、決して納期を変えたことも遅らせたこともない。
2週間きっかり。デザインは彼女、縫製もすべて店で仕上げる。
「次はまた寒くなる前に来ますから、クリスマス用のコートを考えておいて下さいね。」
「任せて。あ、じゃあこの服、ちゃんとおうちの方へお届けしておくわね。」
朋子が服を取り上げると、その動きにきれいにあわせるように、
すっと男性店員が服を受け取る。
「薬師寺さまのところにお願いしますね。」
男は、朋子の声に無言で丁寧にうなずくと、
カウンターのところに服を持って行き、そこにいた女性店員に指示をしている。
落ち着いた低い声だ。
この店は男性の仕立ても行っている。
涼子たちと同い年くらいの、いかにも仕立て屋といったジャケットに身を包んだ控え目な彼の姿が、
この店にいるのが当たり前になったのは、1年ほど前からだろうか。
朋子も信頼をおいているのだろう。
二人の息はぴったりとあっていて、見ていても気持ちがよい。

しばらくして、彼が控えをもってこちらへ歩いてきた。
「あ、ありがとう。じゃあ涼子ちゃん、これが今日のお控えです。ありがとうございました。」
朋子は控えを涼子に手渡すと、深々と頭を下げた。その少し後ろで彼が頭を下げる。
「こちらこそありがとうございました。」
その涼子の声に顔を上げた朋子は、少し戸惑ったように目を泳がせ、
しかし次の瞬間、意を決したように口を開いた。
「涼子ちゃん、あ、あのね、あたし、結婚するの。」
「こら、お客様に!」
後ろの彼が、小さな声で、厳しく朋子をたしなめる。
朋子が驚いて首をすくめた。
…その瞬間、涼子はわかってしまった。
結婚相手が誰かということも、そしてこの2人が今どれだけ幸せかということも。
そしてにっこりとほほ笑んだ。
「いいの、私、後輩だもの。教えてもらって嬉しい。おめでとうございます。」
彼が少し居心地悪げに、しかし丁寧さを崩さずにもう一度頭を下げる。
彼の首にかかっている、使い込まれたしなやかな皮のメジャーが揺れる
きっとすごく仕事に厳しい人だろうから、今みたいに怖い時も多いかもしれない。
でもきちんと職人としての情熱を持った人。
そして間違いなく、先輩を大切にいとおしく思っていくれている人。
朋子が、涼子の手を握り締める。
「結婚式、春にするから、来てね。涼子ちゃんに向かってブーケを投げるから。
おとなしくしていちゃだめよ、絶対に取るのよ。」
…取れぬはずがない。
本気を出したら周りに申し訳ないが、せっかくのチャンスだ、ここは何がなんでもゲットしよう。
「わかりましたわ、必ず頂戴します。」
涼子はぎゅっと朋子の手を握り返した。

ちょうど店を出たところで、前に停めてある車の運転席から、泉田が飛び出してきた。
「あ、警視、ちょうどよかった。例の建物、今令状が取れたと丸山警部から連絡がありました。
向かいますか?」
「もちろん!」
かねてから、行方不明者が何人もそのあたりで最後に目撃されていることで注目していた建物だ。
涼子は泉田があわてて開けた助手席のドアから車に滑り込んだ。
「まったく令状なんて回りくどいこと、よくこのあたしが我慢したわよね。自分で自分をほめてあげたい。」
「…はい。」
「あそこは国有地って看板が出ていたところよ、国有地っていうのは、国民のものじゃないの?
なんで国民が勝手に入っちゃいけないのよ。」
「…その理屈でいけば、官庁街はすべて国民の出入り自由になってしまいますが。」
「そうすればいいじゃない?特に都庁は高額納税者には、知事室のソファーを解放すべきね。」
「…はい。」
泉田は心でつぶやいた。
沈黙は金、どう応えていいかわからない時は「はい」が無難。これぞ官僚の処世術。
「…泉田くんは、あたしが国有地に令状なしに突っ込んだら困る?」
「え?」
ふいに穏やかな声になった涼子の方を、泉田は思わず振り向いた。
その横顔には、いつになくゆったりとした笑みが浮かんでいる。
「困る?」
「ええ、それは困ります。」
「なぜ?後始末に手がかかるから?」
しばらくの沈黙ののち、泉田は答えた。
「…あなたの為によくないと思うからです、警視。」
嘘ではない。いや、口に出してみると、意外と一番真実ではないかと泉田は思った。
後始末にも手がかかっているが、
せっかくの涼子の手柄をもっときれいな形で残せたのではと、いつも後悔しているのも事実だ。
涼子は静かに目を閉じて、つぶやいた。
「…これだから、やっぱりブーケは取っておこうと思うわけよ。」
「は?」
涼子は高く足を組み換え、きっと前を見据えた。
「なんでもない!さあ、飛ばして!一仕事しましょう!」
「はいっ。」
泉田がアクセルをさらに踏み込んで、2人は夕暮れ近い街を走り抜けていった。

優しさは、単に「優しい」と呼ばれる関係には、ないのかもしれない。
むしろ現実の厳しさの中にこそ、本物が隠れているのかもしれない。
私を、いっぱい愛して。
不器用でいい、あなたなりの優しさで包んで。
どんな不定形でも、ちゃんと感じてみせるから。
オートクチュールのようにふんわりと包まれたら、私はもっともっときれいになるから。
だから、だから。ねえ。
Love me tender.
(END)
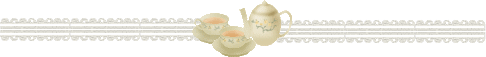
*かわいいお涼サマを書きたかったのですが、力不足あいすみませぬ。
短編集「SP2」に出てくる、先輩方にご登場いただきました。
今後もし本編で出てきて、設定が相違するようなら下げますね。
私、間中先輩大好きです。カーライル先生とか可歩ちゃんも出てほしいな。
30万ヒット、本当にありがとうございました。カメの歩みですが、
また楽しんで頂ければ幸いです。気候の変わり目、お体大切に。